|
聖母の名を戴いたハーブは長い年月の間 疲れた人々の肝臓を癒してきました 【 聖母マリアの名を冠する花 】 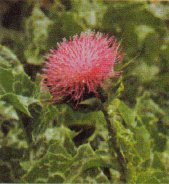 マリアアザミはキク科、オオアザミ属の二年草です。丈が1m以上、開花時には 2mに達することもあり、大きな葉は光沢を帯びてトゲを勢いよく広げています。 日当たりがよく、水はけのよい土壌を好む野生植物で、夏の終わりに、薄い紅紫色の花を咲かせます。薬草としての歴史は古く、ギリシアで善かれた薬草書には「シルポン」という名で紹介され、若葉や芽を食用とすると記されています。 2000年も前からヨーロッパで広く薬用に使われ、そのために栽培もされてきました。しかし、このアザミ・・・マリアという名にしては力強い、たくましい草なのですが、どうしてこの名がついたのでしょうか。 トゲを持つ大きな葉には斑が入っています。実はこれが名前の由来になっているのです。 聖母マリアの乳汁が葉の上にこぼれたという説、また、聖母マリアに捧げるミルクを運んでいる娘が、この菓のトゲに刺されて痛さのあまりミルクをこぼし、葉の上に散ったミルクが白い斑点となって残ったという説があります。どちらにしても聖母マリアにちなむもので、学名はもとより、レディー(Lady/聖母)シスル、ホーリー(HOly/聖なる)シスルという別名を持つのも、すべてここから出ています。 最も古い歴史を持つ西洋ハーブとして、お茶にしたりサラダに使ったりして親しまれ、主に肝臓疾病の治療に使用されてきました。また強壮作用があり、母乳不足や気分の落ちこみなどに効果があるとして用いられました。 ヨーロッパに広く浸透したこのハーブの薬効が、医学的に立証され始めたのは1970年代。種子に含まれるシリマ リンというフラボノイド類が、肝臓病に対して高い有効性を示すことがわかったのです。その有効性を大きく分けると二つ、解毒作用と再生作用です。  まず解毒作用については、シリマリンに抗酸化作用があり、肝細胞膜へ侵入しようとする特定毒素を阻止します。また肝臓病の一因とされる活性酸素を除去する体内物質を増加させるという作用もあると報告されています。 また肝臓の再生能力を上げる作用も認められています。これはシリマリンlがタンパク質合成に関わるRNAポリメラーゼAの働きを高めるので タンパク質合成が盛んになり、解毒しながら肝臓細胞の再生能力が上がるのです。 【 もの静かな働き者をいたわって 】 こうした高い薬効成分から、ドイツでは30年前にシリマリンを医薬品として認可し、肝炎や肝硬変の治療薬として使われています。たくさんの臨床試験が行われていますが、副作用の報告はありません。また、タマゴテンダダケという毒キノコによる食中毒の緊急治療にも使われています。 肝臓は沈黙の臓器といわれます。身体に入った毒を取り去ろうとひたすらに働き、自らを傷めてしまいます。飲酒や喫煙、ストレスなどで身体にどんどん負荷がかかる現代生活では、すすんで肝臓をいたわるのが健康な生活の鍵で あるかもしれません。 |
| キーワード
通信販売「あらま」
長江薬局
ドットサプリ
@美人
ドットコスメ ドクターズサプリメントの
ダグラスラポラトリーズ 高麗人参 (紅参)の 一和高麗人参 |